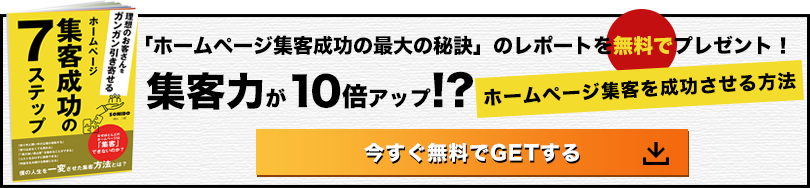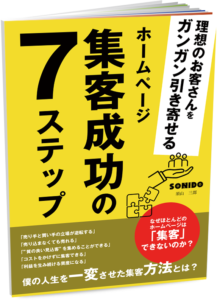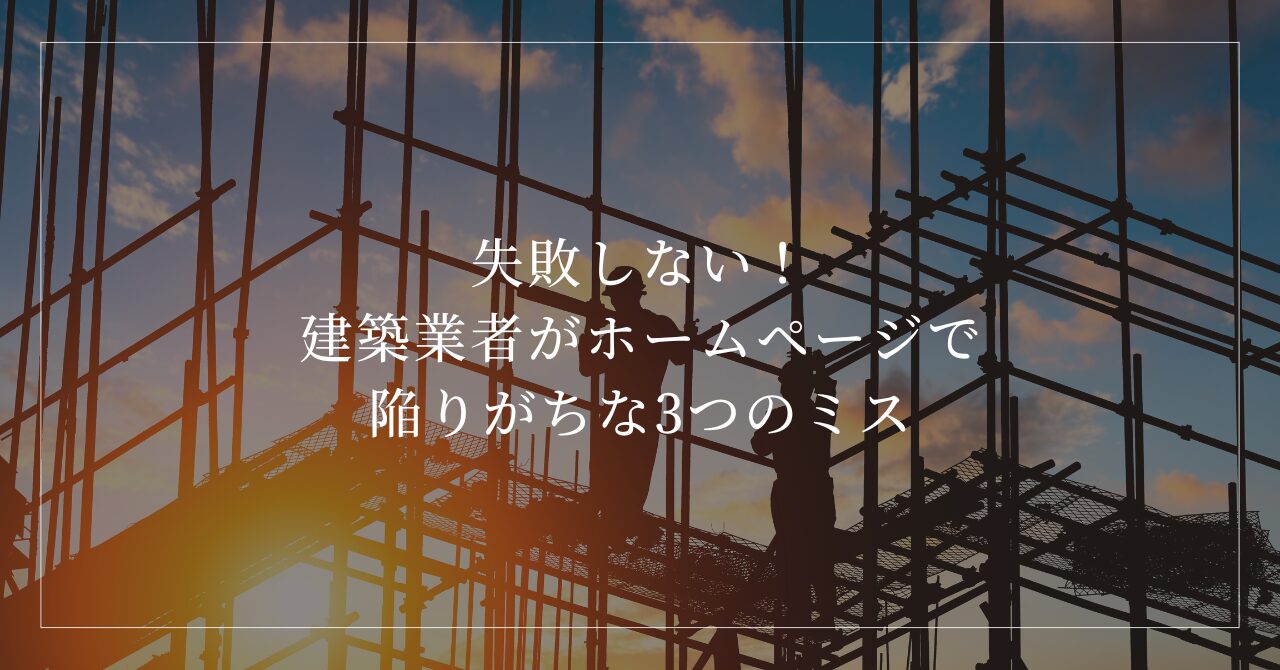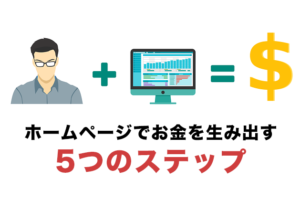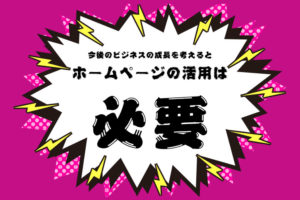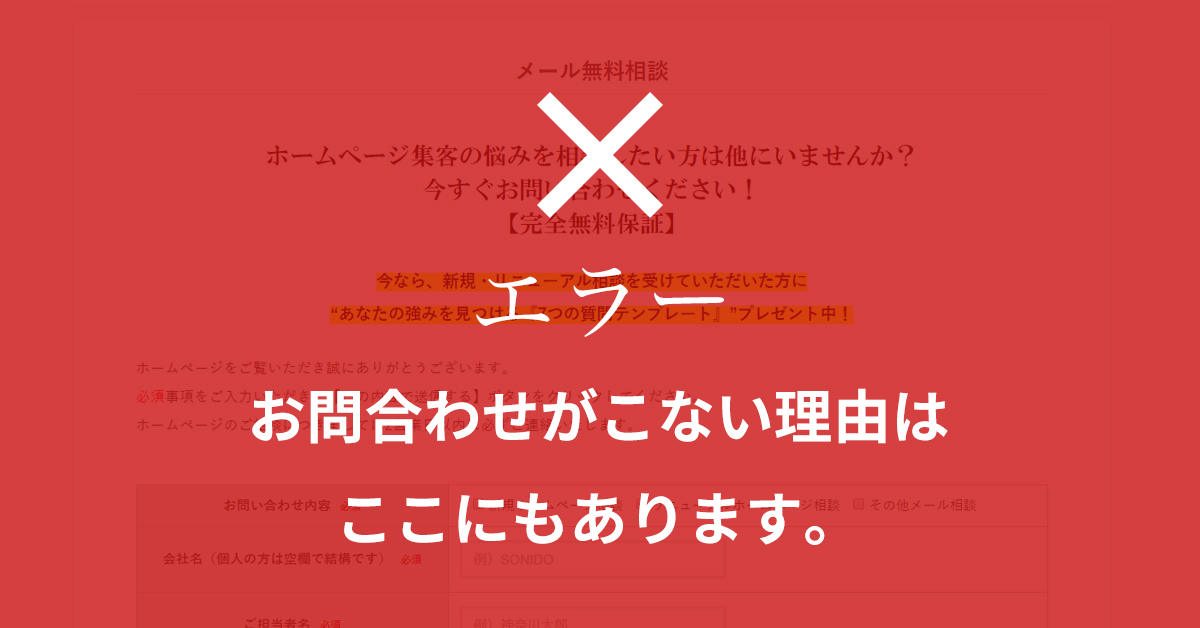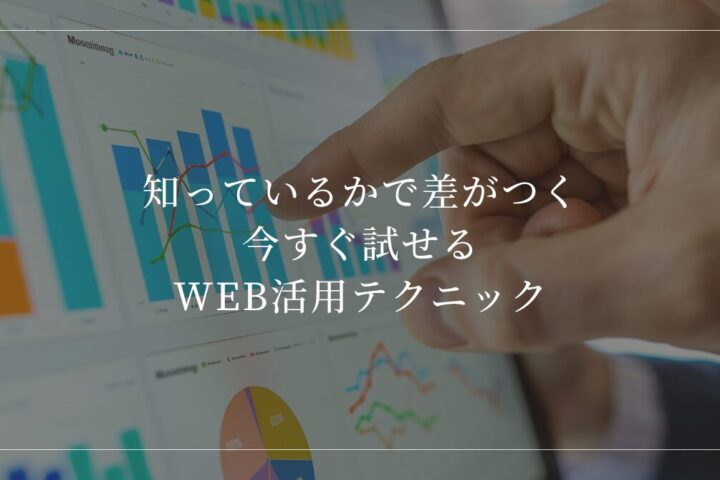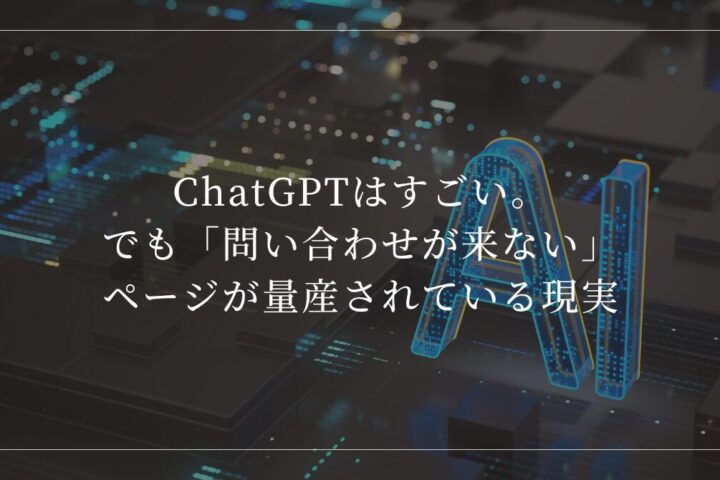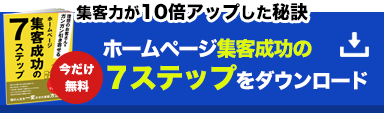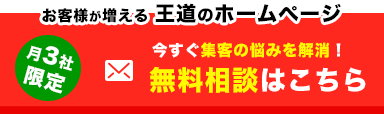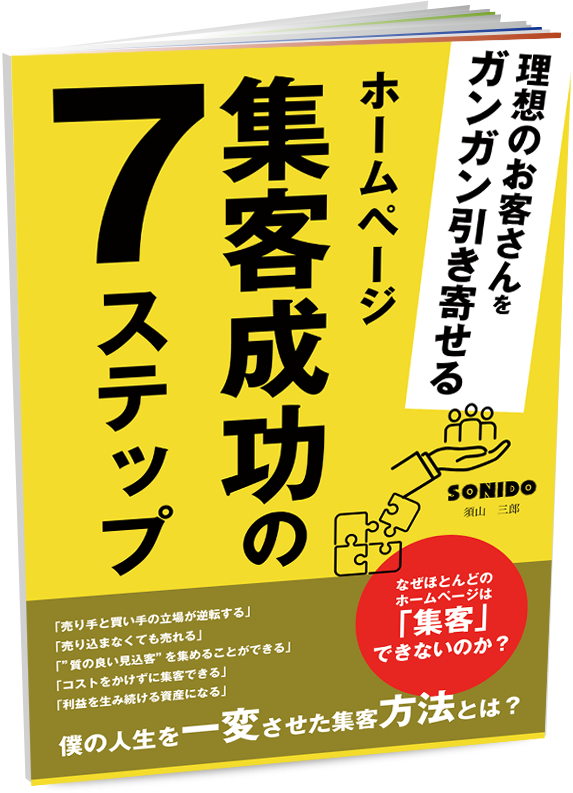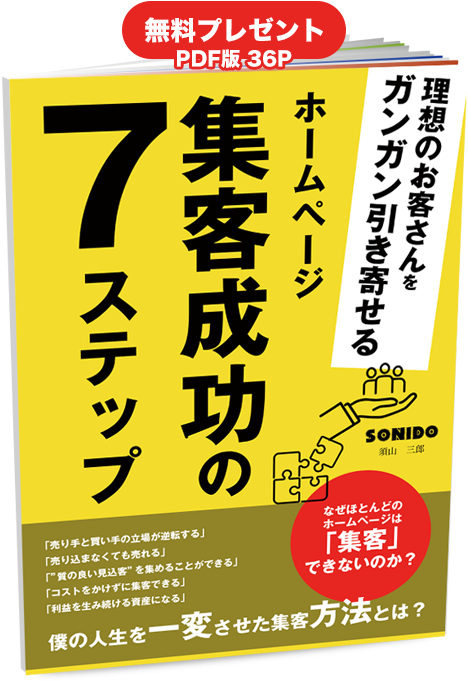AI時代にこそ求められる“人間らしい”コンテンツとは?—検索エンジンと読者が本当に求めるもの
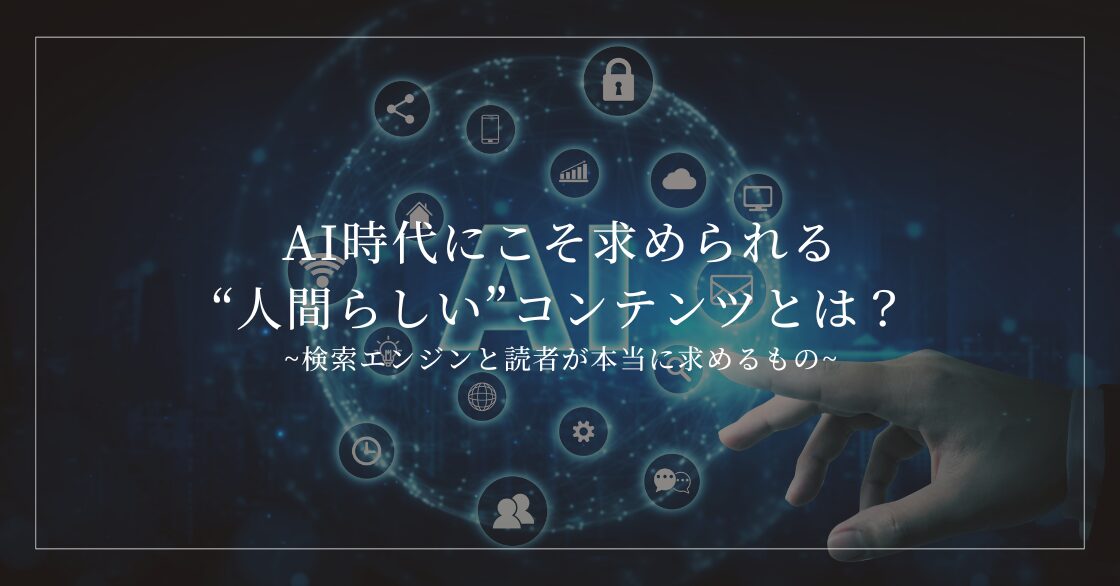
AIが記事を書いてくれる時代になりました。
「ブログ記事を毎日量産!」なんてことも、今やボタンひとつで可能です。
でも、最近こんな話をよく聞きませんか?
- 「AIの記事って、なんか薄っぺらく感じる…」
- 「読んでも記憶に残らない…」
- 「結局、誰が書いてるのかわからないから信用できない…」
実際、Googleも「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を強化し、「本当に価値のあるコンテンツとは何か?」をより厳しく評価するようになっています。
では、AI時代において、人間が書くコンテンツの価値はどこにあるのでしょうか?
そして、どうすれば“人間らしい”コンテンツを作り、検索エンジンと読者の両方に評価されるのでしょうか?
この記事では、AIでは作れない「人間らしいコンテンツ」の特徴と、その作り方について解説します。
目次
1.Googleが求めるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化

「AIが書いた記事です」と言われると、なんとなく不安になる人も多いのではないでしょうか?
それは、記事の内容がどれだけ論理的に正しくても、「この情報、本当に信じていいの?」という疑念が拭えないからです。
Googleもこの点を強く意識しており、単なる情報の羅列ではなく、「経験」「専門性」「権威性」「信頼性」(E-E-A-T)を重視するようになっています。
では、それぞれの要素をどう強化すればよいのでしょうか?
1-1. 経験(Experience)— 実際の体験を語ることの価値
AIには、実体験がありません。
だからこそ、「私が実際にやってみた話」「こんな失敗をした経験」という要素を加えるだけで、一気にコンテンツの価値が高まります。
例えば、「SEO対策の成功事例」について書くなら、単なる理論ではなく、「自社サイトでこういう施策をして検索順位が上がった」「クライアントの事例でこういう結果が出た」といった実体験ベースの話を入れることが重要です。
1-2. 専門性(Expertise)— 深く掘り下げることで信頼感を生む
専門性を証明するには、「他の記事にはない、具体的で深い内容」を提供するのがポイントです。
例えば、SEOの基本について書くなら、「検索意図の重要性」や「E-E-A-Tの活用方法」など、ひとつのテーマを掘り下げて説明することで、「この人は本当に詳しいんだな」と読者に感じてもらえます。
また、専門用語を多用しすぎると読者が離れてしまうので、初心者にもわかりやすい言葉で解説することも重要です。
1-3. 権威性(Authoritativeness)— 信頼できる情報源を示す
Googleは、「その人や企業が、どれくらい業界で認められているのか?」を評価しています。
権威性を高める方法として、以下のような工夫が有効です。
- 専門家との対談やインタビュー記事を掲載する
- 公式なデータや統計を引用する(政府・大学・大手メディアなど)
- 自社の成功事例や実績を明確に示す(例:「〇〇の施策でお問い合わせが○倍に増えた!」)
特に、検索上位にある記事を分析し、「上位サイトが引用しているデータや情報源」を参考にするのは効果的です。
1-4. 信頼性(Trustworthiness)— 透明性を持たせる
最後に、Googleが特に重要視するのが「信頼性」です。
フェイクニュースや誤った情報が溢れる時代だからこそ、読者が安心できる仕組みを作ることが求められます。
信頼性を高めるためには、
- 執筆者のプロフィールを明確にする(どんな経歴の人が書いているのか)
- 実績・証拠を示す(成功事例・証言・レビューなど)
- 出典を明記する(データや統計の引用元を記載)
といった工夫が欠かせません。
AIがいくら賢くなっても、「実際に経験したことを語る」「専門的な視点を加える」「権威ある情報源を活用する」「信頼できる情報を提供する」といった人間ならではの工夫がある記事は、SEOでも読者にも評価されます。
2.そもそもAIには書けない“人間らしい”コンテンツとは?
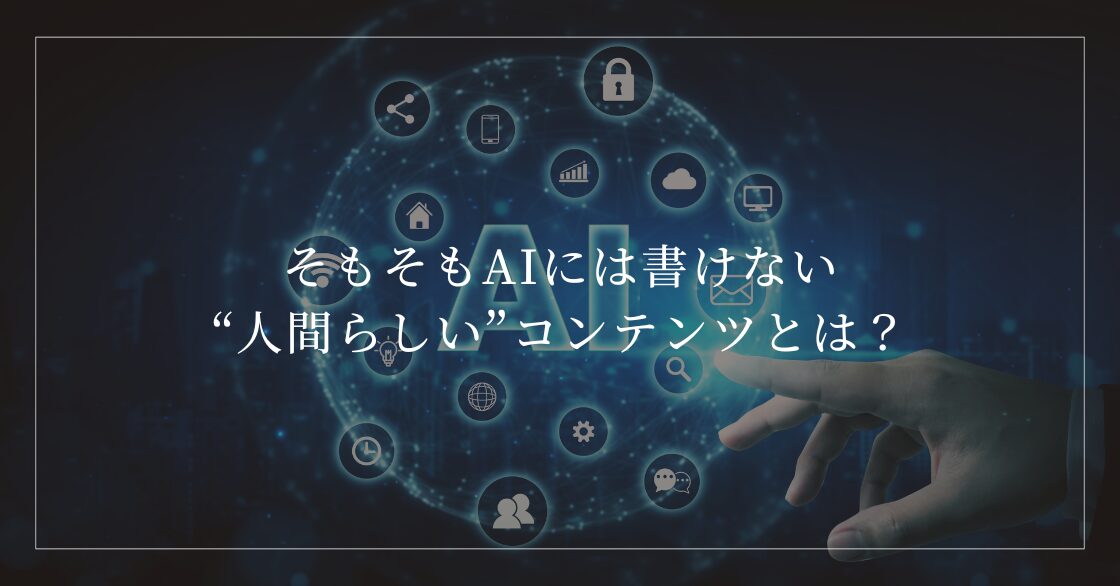
AIは優秀です。
文章を自動生成し、SEOに適したキーワードを盛り込み、短時間で大量のコンテンツを生み出せます。
でも、「読んでいて心に響く」「記憶に残る」そんなコンテンツは、まだAIには難しいのが現実です。
では、AIには書けない“人間らしい”コンテンツとは何か?
具体的に見ていきましょう。
2-1. 感情を伴うストーリーテリング
人は感情で動きます。
そして、感情を揺さぶるコンテンツには、AIには生み出せない「体温」があります。
たとえば、
「SEO対策の失敗例」 について書く場合、AIなら以下のようにまとめるでしょう。
間違ってはいません。でも、どこか味気ない…。
一方、人間が書くとこうなります。
でも、いくら記事を書いても、まったく上位に上がらない。
3ヶ月後に気づいたのは…“初心者向けにロングテールキーワードを狙うべきだった”ということでした。」
こういうリアルな体験談には、“共感”や“感情”が生まれます。
読者は「自分も同じ失敗をしたことがある」と思いながら読み進め、最後まで読もうとするのです。
2-2. 具体的なエピソードや体験談
AIが苦手なのが、「個人の経験」に基づいた文章です。
たとえば、「ホームページ集客の成功事例」を書くとします。
AIは一般論で書くことしかできませんが、人間は“リアルなエピソード”を語れます。
AIが書く記事
人間が書く記事
「私が作成したホームページで、お問い合わせが月3件→40件に増えたお客様がいました。
何をしたかというと…ターゲット層を“塗装業者”に絞り、彼らが検索する“外壁塗装 相場”というワードを軸にした記事を増やしたんです。」
こうした具体的なストーリーがあると、読者は「この方法なら自分も試せる!」と感じ、より信頼してもらえます。
2-3. “人間ならではの視点”を入れる
AIは「データ」をもとに文章を書きます。
だからこそ、データでは語れない“人間の視点”を入れることで、差別化できます。
たとえば、SEOに関する記事を書くなら、
「実際にSEOをやっている人が感じる苦労」や「現場のリアルな裏話」を交えると、読者の共感を得られます。
たとえば…
- 「SEOを学び始めたけど、最初の1ヶ月は全然結果が出なくて焦った」
- 「Googleのアップデートで順位が落ちたとき、絶望感がハンパなかった」
- 「成功した施策の裏には、実は10回以上の失敗があった」
こうしたリアルな気づきや感情を交えたコンテンツは、AIには書けません。
2-4.人間らしいコンテンツの本質とは?
AI時代において、人間が書くべきコンテンツの本質は「感情」「体験」「視点」にあります。
- 感情を込めてストーリーを語る
- 実際の体験を交え、リアルなエピソードを伝える
- データにはない“人間の視点”を加える
これが、読者に「読みたい!」と思わせ、検索エンジンにも評価される“人間らしい”コンテンツなのです。
3.どうやって読者を惹きつけるコンテンツを作るのか?
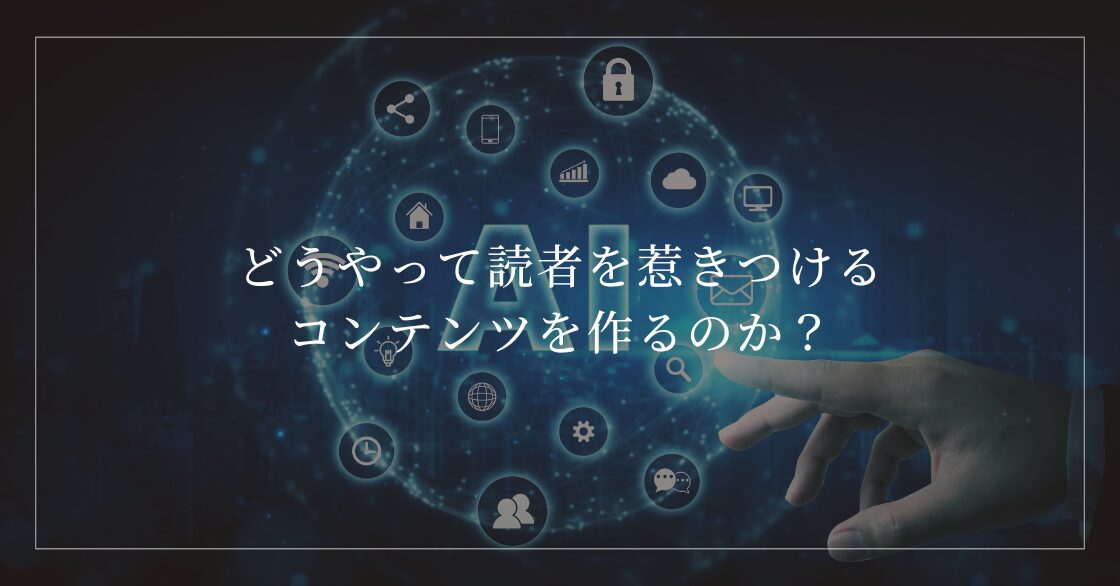
「AIには書けない“人間らしい”コンテンツ」が重要なのは分かった。
でも、実際にどうやって読者を惹きつける記事を書けばいいのか?
ここでは、「最後まで読まれる記事」を作るための具体的な方法を解説します。
3-1. 書き出しで“引き込む”
読者が記事を読むかどうかは、最初の数行で決まると言っても過言ではありません。
では、読者の興味を引くためには、どんな書き出しが効果的でしょうか?
「疑問」を投げかける
読者の興味を引くには、「え?それってどういうこと?」と思わせるのが効果的です。
例:
❌ 「SEOは重要です。検索上位に表示されることでアクセスが増えます。」(普通すぎて印象に残らない)
✅ 「なぜ、SEOに力を入れても“問い合わせが増えない”のか?」(読者の悩みに直結し、興味を引く)
体験談から入る
リアルなエピソードを最初に持ってくると、一気に引き込まれます。
例:
「ホームページからの問い合わせを増やしたいと思って、SEO対策を始めたんです。
でも、最初の3ヶ月はまったく効果なし。
『こんなに記事を書いてるのに、なぜ…?』と頭を抱えました。」
こういう書き出しがあると、「自分も同じ経験がある!」と共感しやすくなります。
3-2. 「読者が知りたいこと」から書く
よくあるミスが、「書きたいこと」を書いてしまうことです。
でも大事なのは、読者が知りたいことを先に書くこと。
これを意識するだけで、記事の質がグッと上がります。
例えば、「ホームページ集客」の記事を書くなら…
❌ 「ホームページとは?」から説明する
✅ 「なぜ、集客できるホームページとできないホームページがあるのか?」から書く
読者は、「ホームページが大事なこと」は知っているけど、
「どうやったら問い合わせが増えるのか?」を知りたいのです。
だから、結論を先に書くのがポイント。
結論 → 理由 → 詳細解説の順番にすると、読者がスムーズに読み進められます。
3-3. 「具体例」で理解しやすくする
人は、抽象的な話よりも「具体例」によって理解が深まります。
たとえば、こんな文章。
❌ 「SEOではキーワード選定が重要です。」(ふーん…で終わる)
✅ 「たとえば、以前“ホームページ制作”というキーワードで記事を書いたことがあります。でも、競争が激しくて検索上位に上がりませんでした。そこで“ホームページ制作 集客 コツ”に変更したところ、上位表示され、問い合わせが増えたんです。」(なるほど!と納得しやすい)
実際にあった話、失敗談、成功談を入れると、読者が「なるほど!」と納得しやすくなります。
3-4. 感情を揺さぶる
人が何かを「行動」するのは、感情が動いたときです。
では、どうすれば読者の感情を揺さぶれるのか?
「共感ポイント」を入れる
たとえば、こんな文章。
「SEOを頑張っているのに、まったく順位が上がらない…。そんな経験、ありませんか?」
この一文だけで、読者は「あるある!」と思う。
すると、続きを読みたくなるんです。
「悔しさ」「驚き」「喜び」を表現する
AIが苦手なのが、「感情表現」です。
たとえば…
「この施策を試したら、3日でアクセス数が2倍に!」
「これを知らずにSEOをしていたなんて、過去の自分をぶん殴りたい!」
こういう表現があると、読者の感情を揺さぶり、記事に引き込まれます。
3-5. 読みやすくする工夫をする
どんなにいい内容でも、「読みにくい」と途中で離脱されてしまいます。
そこで、以下のポイントを意識しましょう。
- 短文を意識する(1文を長くしすぎない)
- 適度に改行する(スマホで読んでもストレスを感じさせない)
- リスト・箇条書きを活用する(ポイントを整理して伝える)
- 見出しを工夫する(パッと見て「読んでみよう」と思わせる)
こうすることで、最後までスムーズに読んでもらえます。
4.これからの時代に求められるコンテンツ戦略
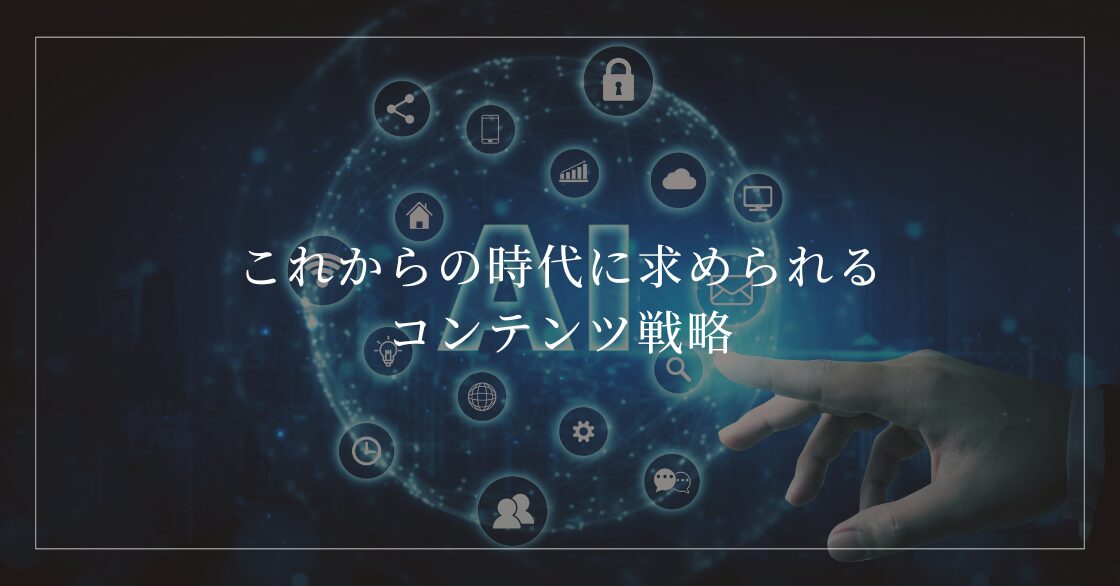
AIが進化し続ける時代。
コンテンツマーケティングも大きく変わろうとしています。
従来の「とにかくSEO対策をして記事を量産する」やり方では、もはや生き残れません。
では、これからの時代に求められるコンテンツ戦略とは何か?
ポイントは以下の3つです。
4-1. “人間らしさ”を前面に出す
AIが書ける記事は、誰でも書ける記事になりつつあります。
だからこそ、「その人だからこそ書ける記事」が求められます。
具体的には…
- 「実体験」を盛り込む(自分だからこそ語れる経験を活かす)
- 「感情」を入れる(苦労した話・成功したときの喜びなど)
- 「ユニークな視点」を持つ(一般論ではなく、自分の意見を伝える)
例えば、「SEO対策の記事」を書くとしても…
人間の記事:「私は“ビッグワード”を狙って失敗しました。でも、ロングテールで狙ったら問い合わせが10倍に!」
こうしたストーリー性のある記事は、AIには書けません。
4-2. 「検索エンジン対策」より「ファン作り」を意識する
SEOは重要ですが、それだけを追いかけても意味がありません。
なぜなら、検索順位は変動するものだからです。
仮に「1位」を取れても、Googleのアップデートで急に順位が落ちることもあります。
そこで必要なのが、「ファンを作る」戦略。
- 読者が「この人の記事を読みたい」と思うコンテンツを作る
- SNSやメルマガなどで直接つながる仕組みを作る
- 「SEO流入」→「リピーター化」を意識した構成にする
つまり、「検索から来た読者」をいかに「自分のファン」にするか?を考えることが大切です。
そのためには、
- 読者の悩みにとことん寄り添う記事を書く
- 「続きが気になる」ようなストーリー構成にする
- 記事の最後に「次に読むべき記事」や「SNSフォロー」へ誘導する
こうした工夫が、長期的に強いコンテンツを生み出します。
4-3. 「AI × 人間」のハイブリッド戦略を活用する
「AI vs 人間」ではなく、これからは「AI × 人間」の時代です。
AIが得意なこと
- データの整理・要約
- キーワード選定
- 検索エンジン向けの文章作成
人間が得意なこと
- 体験談・感情を入れたストーリー
- 独自の視点を入れる
- 読者とのコミュニケーション
たとえば…
1️⃣ AIで記事の骨子(見出し構成)を作る
2️⃣ データや一般論の部分はAIに書かせる
3️⃣ 人間が体験談・感情・共感を入れて仕上げる
こうすることで、効率よく、人間らしいコンテンツを作る ことができます。
まとめ
AIが進化し、誰でも簡単に記事を量産できる時代。
でも、その中で「読まれるコンテンツ」を作るには、人間らしさが不可欠です。
そこで大切なのが、以下の3つのポイントでした。
- 「E-E-A-T」を意識し、経験・専門性・権威性・信頼性を強化する
- AIには書けない「感情」「体験」「ユニークな視点」を盛り込む
- SEO対策よりも「ファンを作る」戦略を重視する
これからのコンテンツ制作では、AIの力を活用しつつ、「人間だからこそ伝えられる価値」 を加えていくことが重要です。
今後も「単なる情報」ではなく、読者の心を動かし、信頼されるコンテンツ を作っていきましょう!